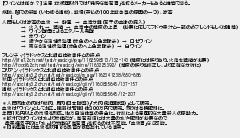[過去ログ] 欧州ワインと人肉食との関連 (1001レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
196(1): 2006/11/20(月) 13:10:05 ID:KCH9fE6B(4/4)調 AA×

2chスレ:psy
2chスレ:wine
2chスレ:mass
2chスレ:giin
2chスレ:giin
197: 2006/11/20(月) 13:26:56 ID:dN7efwJS(4/9)調 AAS
>>194
あんた、動物実験をやりながら「この血液はボジョレーヌーボーみたいだな」なんて考えていたの?
やっぱり普通の人とは感覚が違うね。
で、本当に血液を放置して取れる血清が赤ワイン色だと思っているの?
その色素は活性炭で抜けるの?活性炭って血球を吸着するの?
むちゃくちゃだね。
ちなみに、木直田があわてて「血液について」調べたサイトはここですね。
専門学校卒の検査技師さんも、木直田の知らないことをよく知っていますね。
外部リンク[html]:www2s.biglobe.ne.jp
198: 2006/11/20(月) 14:04:47 ID:dN7efwJS(5/9)調 AAS
木直田って、どうして簡単にできる実験を、言い訳してやらないでおこうとするのか。
実験をすると思った通りの結果がでないのを恐れているのか。
それともそもそもわかっていて嘘を言っているから、実験できないのか。
実験してはいけないという妄想に取り付かれているのか。
いずれにせよ、実験・実証をしないで済まそうとするその態度が、信用をどんどん落としている。
199(1): 2006/11/20(月) 15:47:08 ID:iP98qFvh(4/5)調 AAS
>>183
アイスワインや貴腐ワインはどうですか
200(3): 2006/11/20(月) 17:04:16 ID:kAsL3YCf(1)調 AAS
ワインが人間の血から作られてるとすれば何人くらいの血が必要なのか調べてみた。
ワインの年間生産量は約2650万キロリットル。
外部リンク[html]:www.yitc.go.jp
ヒトの血液量は体重のおよそ1/13で、体重70キロの人なら血液の重さは約5.4kg。
外部リンク:ja.wikipedia.org
世界の人の平均は知りませんが、体重65キロで血液の重さは5キロくらいかと。
血液やワインの比重はだいたい水と同じだろう。
1リットルの水が重さ1キロなので、ワイン生産量を重量に直すと2650万トン。
これを一人分の血液の重さ5キロで割ると
2650万t ÷ 5kg/人 =265億kg ÷ 5kg/人 =53億人
ワインが人間の血から作られてるなら、53億人分の血が毎年必要ってことだ。
ちなみに世界の人口は約64億人。人間はたちまち絶滅しそうだね。
201: 2006/11/20(月) 17:08:05 ID:qWkE9h1P(2/2)調 AAS
もういいよ、家族はこの人を早く病院へつれて行ってあげて。
素人が「ホンモノ」をいじるのは、治療上の禁忌だよ。
202: 2006/11/20(月) 17:09:48 ID:dN7efwJS(6/9)調 AAS
木直田脳内ワイン工場の製法だと、血液は凝固させてしまって残った血清だけ使うから、
実際に使えるのは血液の3分の1以下の量だよ。
203(1): 2006/11/20(月) 17:10:55 ID:PfES8rNK(1/2)調 AAS
フランスとイタリアは確度が高そうだね。
それ以外の国家では
血液酒ではないケースも相応にあるのだろうね。
204(1): 2006/11/20(月) 17:15:00 ID:PfES8rNK(2/2)調 AAS
伝統の製法にこだわる
「本場の伝統もの」が比較的確度が高いでしょうね。
それに対し、本場ではない国家のものに関しては
家畜の血液を使ったり、本当の葡萄酒を造ったりしているのではないのだろうか?
この点に関しては今後更なる調査が必要でしょうね。
205: 2006/11/20(月) 17:39:19 ID:dN7efwJS(7/9)調 AAS
おいっ、調査なんて一つもしてないでしょう。更なるって、あんた。
206: 2006/11/20(月) 19:00:44 ID:rUrDMEhG(1)調 AAS
>>204
脳内調査が始まる前に、とりあえずデパス処方しときますね。
207: 2006/11/20(月) 19:03:02 ID:rx1Aac/Q(1/2)調 AA×
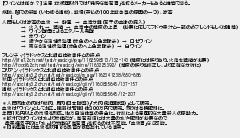
2chスレ:psy
2chスレ:wine
2chスレ:mass
2chスレ:giin
2chスレ:giin
208: 2006/11/20(月) 19:04:13 ID:rx1Aac/Q(2/2)調 AAS
この考え方で現在のところ、全く矛盾しない。
209: 2006/11/20(月) 19:25:05 ID:dN7efwJS(8/9)調 AAS
木直田脳内ワイン工場も、工程が少しずつ変わって来たね。
でも、血清を加熱すると、血清タンパクが変性して出てくるのはどうするの?
結構、たくさん出てくるよ。
210: 2006/11/20(月) 19:28:56 ID:dN7efwJS(9/9)調 AAS
矛盾しないっちゅうか、知識がないから矛盾がわからないだけなんだな。
これまで何度も、矛盾しないって宣言した後に矛盾を指摘されているし。
211: たまにはきいてくれ 2006/11/20(月) 19:41:01 ID:z/uWtYOi(1)調 AAS
お邪魔してすいません
偉そうに書くと良いみたいですよ。
212: 2006/11/20(月) 20:07:59 ID:FgP8xOwd(1)調 AAS
どうでも良いが、赤いのは血のあかなんだっけ?じゃあ、赤ワインには鉄分豊富な
わけだ。でヘムだってどんどん自然分解するはずだが、タンニンと鉄イオンの関係は
どうなんの?まあ基地外に反応するのも何だが、なんと昨日に比べ随分と伸びていたの
で、前をみずに適当にカキコします。もうここで一度書いたかも知れないが、この
キティの着眼点は悪く無いと思うんだよねえ。よく「歴史の定説をひっくり返す」って
やつの筆法に則っているからねえ。通常言われている因果関係を逆転させる、と言う
王道逝っているから。
213: 2006/11/20(月) 21:39:34 ID:ALzOZTHs(1/2)調 AAS
>着眼点は悪く無いと思うんだよねえ。
>よく「歴史の定説をひっくり返す」ってやつの筆法に則っているからねえ。
>通常言われている因果関係を逆転させる、と言う王道逝っているから。
当該学術論議の本質を見抜いていただき
有難うございます。
フランスワインを飲むということは、ヒトを間接的に殺す
という事に他ならない可能性があるという認識が
妥当かどうかの判断を公開の場で行うことは大切と考えています。
「ロックフェラーの禁酒法の本質」はまさにこれだった可能性を考えています。
今後ともご指導いただけますようお願い申し上げます。
214(2): 2006/11/20(月) 21:54:16 ID:ALzOZTHs(2/2)調 AAS
>血清を加熱すると、血清タンパクが変性して
>出てくるのはどうするの?
火入れ(低温殺菌法)は50〜60℃なので、蛋白の変性は
最小限ですむと見られます。この手法で血清の濃縮をかけると推察しています。
>ヘムだってどんどん自然分解するはずだが、
ヘムの分解産物も一部は赤色をしている可能性はあると考えています。
>赤ワインには鉄分豊富
そのとおりですので、果汁の鉄分ではワインの鉄分の豊富さを説明できません。
血液の鉄分:68〜139μg/dl
外部リンク[htm]:www.ne.jp
赤ワイン(新酒)の含有量. 6.0mg/l
www.pref.iwate.jp/~hp1017/kenkyu/naibu/sokuho/sokuho051-100/078.pdf
なお以下のJAの資料によりますと、ブドウ中の鉄分は1mg/kg
外部リンク[html]:www.ja-e-chuo.or.jp
215: 2006/11/20(月) 22:13:54 ID:iP98qFvh(5/5)調 AAS
>>199はどうなのよと
216: 2006/11/20(月) 22:27:29 ID:mL8gU9PW(4/6)調 AAS
>>214
>ヘムの分解産物も一部は赤色をしている可能性はあると考えています。
そんなもの、すぐに還元されて黒くなっちゃうよ。
「赤色をしている可能性」って何だよ。おっさん、自分の知らないことは、
自分の都合の良いように推測するんだな。そういう病気だからしょうがないけど。
217: 2006/11/20(月) 22:30:06 ID:mL8gU9PW(5/6)調 AAS
>>214
>火入れ(低温殺菌法)は50〜60℃なので、蛋白の変性は
>最小限ですむと見られます。この手法で血清の濃縮をかけると推察しています。
自分の血液を数cc取って、実際にやってみればわかるじゃない。
何でやらないの?自分の推測が正しい自信がないんでしょう。
218: 2006/11/20(月) 22:34:43 ID:kFCfQPlj(1)調 AAS
ってかさ、203,204の時点で、もはやスレタイの意味を成していないだろうが。
それとも何か、家畜を食らうことは人肉食なんか!?イタリアとフランス以外は欧州じゃないんか?
あとモノホンさん以外の人達、こいつに何言っても無駄。
こいつはジャンケンして例え負けても「21世紀のハサミは石をも切る事が出来るんだ、つまりばいsdbかs」
って事になるのは目に見えているよ。
もっと建設的なスレで書き込もうぜ、って俺もな。
219: 2006/11/20(月) 23:02:47 ID:mL8gU9PW(6/6)調 AAS
餌を蒔くと、面白い妄想が生まれたり、いくら何でも無理のある言い訳をしたりするのを楽しんでいます。
220(4): 200 2006/11/20(月) 23:24:18 ID:3y0Otrt8(1)調 AAS
>>203
なるほど「フランスとイタリアは血を使ってるけど他は違う」と?
でもフランスとイタリアだけで
全世界のワインの生産量の40パーセントくらいを作ってるよ。
>>200 で計算した数字に0.4をかけても20億人くらいになる。
毎年20億人分の血液が必要だね。
で、全世界の人口を合わせても64億人しかいない。
221(1): 2006/11/21(火) 07:20:50 ID:/Doz+eJD(1/8)調 AAS
>>220
ソースを示してください
222(1): 2006/11/21(火) 07:23:19 ID:/Doz+eJD(2/8)調 AAS
>>220
またそれだけの量のワインを生産するたけに必要な
ブドウ畑面積がフランスとイタリアに本当にあるか、ソースを示して
論じてもらえますか?
223: 2006/11/21(火) 07:26:21 ID:/Doz+eJD(3/8)調 AAS
>>220
また赤ワインの鉄分の元素循環収支があわない点についても
説明してもらえますか?
224: 2006/11/21(火) 07:32:38 ID:/Doz+eJD(4/8)調 AAS
258 :無党派さん :2006/11/20(月) 23:39:34 ID:7cB3vDQG
伊情報機関トップを更迭 CIAの拉致に関与の疑い(Asahi.Com)ーアメリカは今も拉致している
外部リンク[html]:www.asyura2.com
投稿者 ああ、やっぱり 日時 2006 年 11 月 20 日 23:06:03: 5/1orr4gevN/c
伊情報機関トップを更迭 CIAの拉致に関与の疑い
2006年11月20日21時46分
外部リンク[html]:www.asahi.com
225: 2006/11/21(火) 07:34:45 ID:/Doz+eJD(5/8)調 AAS
ワイン生産が盛んなイタリアでも以下URLに示したように
大量の外国人労働者が毎年、行方不明になっており、
彼らの死(血)がイタリアワインになっている可能性が否定できない状況にあります。
【イタリア】トマト畑で働かされる“農民奴隷” 劣悪な労働条件の中、逃亡者は殺害 地元警察もマフィアを恐れて摘発に及び腰[1027]
2chスレ:news5plus
226: 2006/11/21(火) 07:40:14 ID:/Doz+eJD(6/8)調 AAS
ワインは欧州の「暗部中の暗部」なのだろう
227: 2006/11/21(火) 08:01:27 ID:/Doz+eJD(7/8)調 AAS
ワイン供給量と血液供給量との収支があわないという「ご指摘」
のソースが事実ならば、人間の血液を使っているのは
フランスワイン、イタリアワインの中でも特に老舗のメーカーだけなのかもしれない。
そのために両国は世界中から人間の血液をあらゆる裏手段で
集めているものと見られる。イタリアが東欧から季節労働者を大量に受け入れ
毎年殺害しているとの記事やフランスが熱波という名目で国内で大量に死亡者を
出したといった記事と関連がある可能性も考えていかざるをえない。また
イラク戦争前のイラクでのフランス利権の実態やユーゴ空爆での役割、更には
フランス外人部隊の機能も考察する必要がある。
圧倒的な血液不足が続く業界構造があるならば、拉致・戦争を含め
あらゆる手段で、血液入手に努めると考えない方がむしろ不自然ではないか。
そもそも英仏の100年戦争はワインが戦争目的の一つだったと言われている。
その上で不足している分は、家畜の血液を使っているのであろう。
家畜のバイオマスもかなり大きい。相当の血液量を供給できるだろう。しかし
フランスやイタリアの老舗はあくまでも「人間の血液」にこだわるであろう。
「人間の血液」の愛好家が欧州貴族に多い以上、それだけの品質のニーズがあると
見た方がよいと考える。
また発酵前に葡萄果汁を相当量ブレンドする事によって糖分を高める事(補糖)によって
発酵後のアルコール度を高めると同時に、一瓶あたりの血液消費量を減らす手法も
使われていると推察できる。
228: 2006/11/21(火) 08:06:36 ID:/Doz+eJD(8/8)調 AAS
ワインは欧州の「暗部中の暗部」なのだろう
外部リンク[html]:www.asahi.com
2chスレ:news5plus
ワイン供給量と血液供給量との収支があわないという「ご指摘」
のソースが事実ならば、人間の血液を使っているのは
フランスワイン、イタリアワインの中でも特に老舗のメーカーだけなのかもしれない。
そのために両国は世界中から人間の血液をあらゆる裏手段で
集めているものと見られる。イタリアが東欧から季節労働者を大量に受け入れ
毎年殺害しているとの記事やフランスが熱波という名目で国内で大量に死亡者を
出したといった記事と関連がある可能性も考えていかざるをえない。また
イラク戦争前のイラクでのフランス利権の実態やユーゴ空爆での役割、更には
フランス外人部隊の機能も考察する必要がある。
圧倒的な血液不足が続く業界構造があるならば、拉致・戦争を含め
あらゆる手段で、血液入手に努めると考えない方がむしろ不自然ではないか。
そもそも英仏の100年戦争はワインが戦争目的の一つだったと言われている。
その上で不足している分は、家畜の血液を使っているのであろう。
家畜のバイオマスもかなり大きい。相当の血液量を供給できるだろう。しかし
フランスやイタリアの老舗はあくまでも「人間の血液」にこだわるであろう。
「人間の血液」の愛好家が欧州貴族に多い以上、それだけの品質のニーズがあると
見た方がよいと考える。
また発酵前に葡萄果汁を相当量ブレンドする事によって糖分を高める事(補糖)によって
発酵後のアルコール度を高めると同時に、一瓶あたりの血液消費量を減らす手法も
使われていると推察できる。
2chスレ:wine
229: 2006/11/21(火) 08:39:55 ID:9vBXOXU+(1/2)調 AAS
ここに書かれていることはすべて妄想です。
本当にありがとうございました。
230(6): 200 2006/11/21(火) 09:16:23 ID:1A2ur9Uy(1)調 AAS
>>221
>ソースを示してください
外部リンク[html]:www.yitc.go.jp
これ>>200で引用したのと同じページだよ。ちゃんと読んでる?
>>222
後は自分で調べてね。
231: 2006/11/21(火) 11:08:38 ID:2/aPCeh8(1/5)調 AAS
223 :Appellation Nanashi Controlee:2006/11/21(火) 07:26:21 ID:/Doz+eJD
>>220
また赤ワインの鉄分の元素循環収支があわない点についても
説明してもらえますか?
232(1): 2006/11/21(火) 11:52:00 ID:IXtWiuyh(1/2)調 AAS
>>179
>>182
試しに血液中の鉄分量を計算してみたよ。
計算間違ってるかも。詳しい方、訂正よろしく。
血液中のヘモグロビン量(血色素量,Hb)は、先生ご紹介のページ
外部リンク[htm]:www.ne.jp
によれば男で14〜18g/dl,女で12〜16g/dl。まあ大体15g/dlってとこか。
wikipediaの「ヘモグロビン」の項
外部リンク:ja.wikipedia.org
によれば、
「ヘモグロビン分子全体の分子量は約64,000であり、ヘムを4つ含む。
ヘムは価数が2価の鉄原子を中央に配位したポルフィリン誘導体である。」
だそうだ。ヘモグロビン1分子とその中に含まれる鉄(原子4つ分)の重量比は
鉄の原子量が55.845だから
64,000 : (55.845 × 4) = 64,000 : 223.38 ≒ 287 : 1
まあ大体300対1くらいだね。
というわけで血色素量を300で割れば血液中の鉄分量が求まって
15g/dl ÷ 300 = 15000mg/dl ÷ 300 = 50mg/dl = 500mg/l
約500mg/lってことは赤ワイン(6mg/l)の83倍もあるぞ。
血液からワインを作るとしたら、火入れで濃縮するどころか80倍くらいに薄めないと。
233(1): 2006/11/21(火) 12:07:01 ID:2/aPCeh8(2/5)調 AAS
血清という言葉の意味をご存知ですか?
234(2): 2006/11/21(火) 12:10:04 ID:2/aPCeh8(3/5)調 AAS
血液中のヘモグロビン量ではなく、
血清中のヘモグロビン量が問題になるのですよ。
ただワイン製造ステップでの静置作業だけでは
完全には分離できませんので、若干の血球が上澄みに混入するのは
避けられませんが…。
235: 2006/11/21(火) 12:12:42 ID:OGd77Fhp(1)調 AAS
最近のフランス人はワインよりビールを好み
ワイン農家は減反をしいられているのが実状
236: 2006/11/21(火) 12:15:34 ID:2/aPCeh8(4/5)調 AAS
>最近のフランス人はワインよりビールを好み
>ワイン農家は減反をしいられているのが実状
フランス政府が、ここでの論議の正当性をお認めになった
という事でしょうか?
237: 2006/11/21(火) 13:43:45 ID:UX4H2T3s(1)調 AAS
いやぁなかなか着眼点が斬新だ
その発想はありませんでしたね
で、先生は本来何について専攻しているんですか?
238: 2006/11/21(火) 14:09:47 ID:tLcsP2yJ(1/3)調 AAS
>>234
おっさん、相変わらず想像だけでものを言っているんだな。
だから、血液をほっておいたらどうなるのか試してみなって。
大部分が血餅として固まってしまって、血清なんてちょっとしか
取れないよ。残った血清の色って、そんなに赤くないよ。
やってみてごらんって。嘘がばれるのがいやだから、やらないんでしょう。
239: 2006/11/21(火) 14:11:45 ID:tLcsP2yJ(2/3)調 AAS
>>233
血清と血漿と血液の違いを昨日知ったおっさんが、えらそうに言いなさんな。
おまけに、よそのサイトの文章をそのまま引用して、さも知っていたようなふりをして。
240: 2006/11/21(火) 14:27:51 ID:IXtWiuyh(2/2)調 AAS
>>234
ああ、>>195以前と>>196以降で先生の脳内ワイン製法が変わってるのね。
最初は血液だって言ってたくせに。
まあ血液だろうが血清だろうがデタラメの妄想ってことに変わりないけどね。
241: 2006/11/21(火) 14:47:01 ID:2/aPCeh8(5/5)調 AAS
確かに数時間の静置では変化しませんが、
ワイン製造過程で見られるような形で
血液を冷暗所で数週間、静置しておけば
やはり沈殿物が相応に離しますよ。
もしそうでないと言われるならば
それが起きなかった実験条件を示してもらえますか?
242: 2006/11/21(火) 14:53:24 ID:tLcsP2yJ(3/3)調 AAS
木直田脳内ワイン工房では、どんな環境で血液を静置しておくんですか?
気温とか湿度とか。
あと、50度とか60度なんて加熱したら、血清タンパクはかなり変性してしまうよ。
嘘だと思うなら、先生、60度のお風呂にしばらく入っていてごらん。
243(1): 2006/11/21(火) 18:20:42 ID:7PWMk5vw(1/4)調 AAS
集めた血液にクエン酸ナトリウムを添加して
4℃程度の冷暗所で数週間放置すれば、
血清分離は可能と見られます。
244: 2006/11/21(火) 18:22:33 ID:7PWMk5vw(2/4)調 AAS
火入れ(低温殺菌法)での濃縮の際に
血清タンパクが若干、変性しても何ら問題は来たしません。
そもそもヘムは低分子化学物質であり蛋白ではありません。
245: 2006/11/21(火) 18:25:05 ID:EGJLF8Fo(1)調 AAS
つーか、「真実を研究することには圧力がかかる」みたいな事言ってたわけだが
その真実を公表するオマエには圧力かからんのかと小一時間問い詰めたい
246: 2006/11/21(火) 18:30:18 ID:7PWMk5vw(3/4)調 AAS
圧力はかかっていますよ。
247: 2006/11/21(火) 18:30:47 ID:4xWyW0/I(1/2)調 AAS
>>230についてはどうなの?
都合悪いからスルー?w
248: 2006/11/21(火) 19:33:38 ID:fm9n+Zoi(1/3)調 AAS
>>243
可能かは別にして、中世にクエン酸ナトリウムを精製して血液に添加していたの?
249: 2006/11/21(火) 19:40:54 ID:7PWMk5vw(4/4)調 AAS
要はキレート剤なら何でもよいでしょうので
多様な有機酸も使えるのではないですか?
有機酸発酵は容易です。
250: 2006/11/21(火) 21:04:32 ID:lod9J4NI(1/18)調 AAS
【とりあえず雑感:1】
旧約聖書に「血液を飲む事が当時、習慣だった」と記述されていた
という事が事実ならば、古代・中世はそれに相当する状況だったのだろう。
西洋は日本と比べ水環境は悪い。水質は悪く、飲料水を探すのが難しかった。
よって一般的・日常的に血を飲んでいたと見られる。
血は、「肉を提供した野生動物」の血が使われていたであろう。
対象の野生動物は人間の場合もあれば獣の場合もありえたと推察できる。
そもそも狩猟文化とはそういうものだ。
251(1): 2006/11/21(火) 21:11:51 ID:lod9J4NI(2/18)調 AAS
【とりあえず雑感:2】
獣や人間を屠って流れ落ちる血を当然、容器で受ける。
容器にためて血を飲む事になる。
その容器の衛生環境が悪く、他の食物が若干、残っていたりする場合も
あっただろう。そもそも当時は衛生環境という概念自体がない。そういった場合は、
残っている食物の滓は自然に有機酸発酵する。酢酸やクエン酸などが
自然に生産される。
そして、それらの有機酸類は血液凝固を防ぐ抗凝固剤になりえ、
血液をその容器に加えても凝固しにくくなることも当然ありえたと推測できる。
そしてその凝固しなくなった血液が、その容器の中で自然にエタノール発酵した。
それがワインのプロトタイプだろう。ただこういった場合は糖濃度が低いので
アルコール度数は低く、酒という感覚はなかったかもしれないが。
252: 2006/11/21(火) 21:15:28 ID:4xWyW0/I(2/2)調 AAS
で、>>230についてはどうなのよ?
253: 2006/11/21(火) 21:17:52 ID:lod9J4NI(3/18)調 AAS
ちょっと待ってね。
254: 2006/11/21(火) 22:29:22 ID:fm9n+Zoi(2/3)調 AAS
>>251
「血液は凝固する」ということが、やっとわかったんだね。
でもさ、血液ってあっという間に凝固しちゃうから、
木直田が死体をむさぼり食っても、血は固まっちゃって、流れてはこないよ。
自分の血液をちょっとだけ取って、どれくらいで固まるか、試してみなよ。
(5分たって固まらなかったら、それは病気だから病院に行ってね。)
255: 2006/11/21(火) 22:48:08 ID:lod9J4NI(4/18)調 AAS
それを言えば献血ができないでしょ。
抗凝固剤(キレート)はそのためにあるのでしょ。
256: 2006/11/21(火) 22:49:12 ID:lod9J4NI(5/18)調 AAS
●フランスのワイン生産者がデモ行進−政府に補償を求める− タイムズ 04-12- 9
フランスのワイン生産者が8日、国内各地で、農業機械やトラクターなどを連ね、
デモ行進を行った。輸出や国内販売の減少を受け、政府に補償を求めている。
南部地域のアビニョンでは約7000人がデモに参加。
農業機械に「政府はワイン生産者の死を望んでいる!」と書いた横断幕を張り付けて行進。
「ブルゴーニュ」や「ボージョレー」の産地である東部地域のマコンでは、
同様に約2500人がデモに参加した。
257: 2006/11/21(火) 22:50:51 ID:lod9J4NI(6/18)調 AAS
●フランスのワイン生産者がデモ行進−政府に補償を求める− タイムズ 04-12- 9
ワイン生産者は、国内でのワイン消費量の減少について、
政府の健康キャンペーンや飲酒運転に対する規制強化が一因とも指摘している。
ワインの一人当たり年間消費量は1960年代前半にはおよそ100リットルだったのに対し、
02年には58リットルにまで減少した。
258(1): 2006/11/21(火) 22:53:41 ID:9vBXOXU+(2/2)調 AAS
ワインの定義って『ぶどうの果汁をアルコール発酵させたもの』だから
血液を発酵させたものを飲む慣習があったとしても、それは飽くまでも
『血液を発酵させたもの』を飲んでいただけであって、ワインとは呼ばないし
ワインとの関係もないんだよ。
259: 2006/11/21(火) 22:56:35 ID:lod9J4NI(7/18)調 AAS
1.ワインが純粋な葡萄酒ならば何故、フランス政府は
ワインに対するネガティブな健康キャンペーンを行うのか?
2.ワインが純粋な葡萄酒なら何故、鉄分が葡萄そのものより
一桁近く多いのか?元素循環の収支があわない。
3.ワインが純粋な葡萄酒ならば、何故、フランス国民は
この40年間で半分近くまでワイン消費量を落としたのか?
4.ワインが純粋な葡萄酒ならば、何故、フランス外人部隊は
コルク栓にフランス外人部隊の刻印をつけたワイン製造を行っている
とする資料が確認できるのか?またフランス外人部隊がワイン製造地域に
部隊を構えているのか?
260: 2006/11/21(火) 22:59:36 ID:lod9J4NI(8/18)調 AAS
その一方で、フランス等が入手可能な血液量と
フランス等でのワイン生産量とが全く桁があわないのは確かに事実。
この矛盾をどう考えるのか?
261: 2006/11/21(火) 23:02:22 ID:lod9J4NI(9/18)調 AAS
この矛盾に答える事が可能な答えは
>>258の方が指摘されたように、
フランス等の伝統国のワインには多様な種類がある
という事であろう。
262: 2006/11/21(火) 23:04:37 ID:lod9J4NI(10/18)調 AAS
しかし多様であるといっても
いずれも何らかの形で血液を使っていないと、
以下の矛盾に答える事はできないであろう。
2.ワインが純粋な葡萄酒なら何故、鉄分が葡萄そのものより
一桁近く多いのか?元素循環の収支があわない。
263: 2006/11/21(火) 23:08:47 ID:lod9J4NI(11/18)調 AAS
1.血清に果汁で補糖してエタノール発酵させた血液酒
2.果汁に血球(血餅)を添加してエタノール発酵させた血液酒
の2種類があると仮定した場合、今までの論議に全て矛盾しなくなる。
264: 2006/11/21(火) 23:14:40 ID:lod9J4NI(12/18)調 AAS
NHKのプロジェクトXにて、北海道ワインの製造者の苦労話
が題材になった事がある。
北海道で葡萄を栽培して、あらゆる方法で葡萄酒の作成を試みたが
葡萄だけでは、どうしてもワインの味がしなかったという。
そのためドイツに長期研修に行き、長期の研修を積み、
ドイツ人技師の信頼を勝ち得た後になって初めて、
「本当は教えてはいけない秘伝の添加物」を教えてもらったという。
そしてそれを北海道で使ってみたら初めてワインの味がしたという。
それがこれではないか?
265: 2006/11/21(火) 23:19:49 ID:lod9J4NI(13/18)調 AA×

266: 2006/11/21(火) 23:21:58 ID:lod9J4NI(14/18)調 AAS
現在、流通しているワインが、上の4,5で
ワインの名称を変える事で対応しているならば、今までの論議に
全て矛盾しない。また鉄分の元素循環上の以下の矛盾にも答える事が可能となる。
2.ワインが純粋な葡萄酒なら何故、鉄分が葡萄そのものより
一桁近く多いのか?元素循環の収支があわない。
267: 2006/11/21(火) 23:22:56 ID:lod9J4NI(15/18)調 AAS
北海道で葡萄を栽培して、あらゆる方法で葡萄酒の作成を試みたが
葡萄だけでは、どうしてもワインの味がしなかったというNHK番組は
これを言っていたのではないか。
268: 2006/11/21(火) 23:27:37 ID:lod9J4NI(16/18)調 AAS
フランス外人部隊に志願した日本人たちの話
外部リンク[html]:iori3.cocolog-nifty.com
「ここではワインも造っててラベルもコルクの印も
外人部隊のマーク入り。手伝いにいかされた志願者が
土産にコルク栓を皆で持ってっててたよ 」
269: 2006/11/21(火) 23:33:05 ID:lod9J4NI(17/18)調 AAS
ワインを生産する村であると同時に、
Nogentには外人部隊がある。
外部リンク[html]:www.chansonkame.com
270: 2006/11/21(火) 23:55:46 ID:lod9J4NI(18/18)調 AAS
この問題を科学的に解決する最も簡単な方法は
ワインと葡萄果汁双方に対する網羅的な原子吸光分析もしくはICPだろう。
更に決定的な確認方法は複数の色素分子のHPLC分離とNMR等での構造決定だろう。
現時点でのデータではワインはその材料の一つに
血液を使っている可能性が否定できない。
==============
赤ワイン(新酒)の含有量. 6.0mg/l
www.pref.iwate.jp/~hp1017/kenkyu/naibu/sokuho/sokuho051-100/078.pdf
なお以下のJAの資料によりますと、ブドウ中の鉄分は1mg/kg
外部リンク[html]:www.ja-e-chuo.or.jp
271(1): 2006/11/21(火) 23:59:04 ID:fm9n+Zoi(3/3)調 AAS
木直田の脳内では、そんなに昔から効果のある抗凝固薬が使われていたのか。
アスピリンの発明なんて大したことなかったんだね。
で、抗凝固薬を使って固まらなくしちゃうと、静置しておいても血清は分離できないよ。
輸血用の血液は全血でも、放置しておいて分離しないでしょう。
血液について知識がないから、いちいち、言っていることが矛盾しているよ。
272(1): 2006/11/22(水) 00:08:55 ID:gdDZz6mh(1/4)調 AAS
食用ブドウの鉄分数値を見て、ワイン用ブドウと混同させる辺りも
醸造学とワイン作りについてド素人な証拠だ。
澱引きも果汁の段階で行う作業じゃないしな。
っつても分からないだろうけど。
273: 2006/11/22(水) 00:09:41 ID:Bf5s+tOT(1)調 AAS
968 名前:最低人類0号 :2006/11/21(火) 23:30:28 ID:7l+e82wP
>>965
実物見に行ったのか?
俺は同じだと思ったぞ
974 名前:最低人類0号 :2006/11/21(火) 23:57:34 ID:XQxxuNc+
>>968
見に行ったっつーか
今日初めて一致した
274: 2006/11/22(水) 00:09:45 ID:81OpjFw/(1/9)調 AAS
だから>>230の疑問に答えろよwwwwwwwwwwwwwwwww
275: 2006/11/22(水) 00:14:19 ID:GVSsKEpg(1/12)調 AAS
>>271
>抗凝固薬を使って固まらなくしちゃうと、
>静置しておいても血清は分離できないよ。
それは嘘ですね。貴方は本当に血液学関係者ですか?
「血液を採り抗凝固剤 (血液凝固を阻止する薬剤) を加えて長時間放置すると,
血球 (有形成分) 約45%と血漿 (無形成分) 約55%に分かれます (図 2) 」
外部リンク[html]:www2s.biglobe.ne.jp
276: 2006/11/22(水) 00:16:37 ID:0RNKeWH3(1/5)調 AAS
やっぱり、血清と血漿の区別がついていないの?
血球と血漿に分かれるって書いてあるじゃない。
277: 2006/11/22(水) 00:18:08 ID:GVSsKEpg(2/12)調 AAS
ステップ5で進む場合は、血清と血餅に分離する必要すらない。
−−−−−−−−−−−−−−−
ステップ1: 血液をそのまま飲んでいた (旧約聖書時代)
↓
ステップ2: 偶然、自然発酵した血液を飲むようになった
↓
ステップ3: 血液を放置し得られた血清を火入れ濃縮し
エタノール発酵させたもの (恐らく中世)
↓
ステップ4: ステップ3の血清に果汁で補糖を行ったものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
↓
ステップ5: 豊富に得られる果汁に血球もしくは血液を添加したものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
278: 2006/11/22(水) 00:25:26 ID:GVSsKEpg(3/12)調 AAS
確かに血清分離にはクエン酸ナトリウムはいりませんね。
=========
体内では固まらずに流れている血液も、採血した血液は採った瞬間から
固まり始めます。そのまま放っておくと、初めはサラサラしていた血液が
ドロドロと粘度を増してきて、ついには固まり、
さらに時間がたてば赤い血餅(けっぺい)と呼ばれるかたまりと、
淡黄色〜黄色の血清(けっせい)とよばれる液体に分離します。
大半の検査はこの血清の部分を使っています。検査室では遠心分離機
(えんしんぶんりき)という専用の機械にいれてきちんと分離させます。
279: 2006/11/22(水) 00:27:32 ID:GVSsKEpg(4/12)調 AAS
>食用ブドウの鉄分数値を見て、ワイン用ブドウと混同させる辺りも
種が違わないこの程度の差ならば
鉄濃度は倍も変わらないでしょうね。
280(1): 2006/11/22(水) 00:31:57 ID:gdDZz6mh(2/4)調 AAS
だからド素人と言ってるんだよ
281(1): 2006/11/22(水) 00:33:35 ID:GVSsKEpg(5/12)調 AAS
>澱引きも果汁の段階で行う作業じゃないしな。
ステップ5: 豊富に得られる果汁に血球もしくは血液を添加したものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
この方向性で進む場合は、そうなりますね。
==========
澱とは、葡萄の果肉や果皮の分解された物、
発酵を終えた酵母、ワイン中の酸味の成分(酒石酸)が
結晶化した酒石と呼ばれる物、ワイン中の色素やタンパクなどが
他の成分と結びついて沈んだ物などを総じて呼ばれる物ですが、
これを適切なタイミングでワインから取り除かないと、
澱から溶け出した成分でワインの味を悪くしてしまいます。
外部リンク[htm]:www.sommelier.jp
282(1): 2006/11/22(水) 00:34:34 ID:GVSsKEpg(6/12)調 AAS
>>280
ソースをお示しください
283(1): 2006/11/22(水) 00:36:24 ID:GVSsKEpg(7/12)調 AAS
1.ワインが純粋な葡萄酒ならば何故、フランス政府は
ワインに対するネガティブな健康キャンペーンを行うのか?
2.ワインが純粋な葡萄酒なら何故、鉄分が葡萄そのものより
一桁近く多いのか?元素循環の収支があわない。
3.ワインが純粋な葡萄酒ならば、何故、フランス国民は
この40年間で半分近くまでワイン消費量を落としたのか?
4.ワインが純粋な葡萄酒ならば、何故、フランス外人部隊は
コルク栓にフランス外人部隊の刻印をつけたワイン製造を行っている
とする資料が確認できるのか?またフランス外人部隊がワイン製造地域に
部隊を構えているのか?
5.ワインが純粋な葡萄酒ならば、何故、ロックフエラーは禁酒法を通したのか?
284: 2006/11/22(水) 00:36:54 ID:81OpjFw/(2/9)調 AAS
>>283
>>230
285: 2006/11/22(水) 00:45:10 ID:0RNKeWH3(2/5)調 AAS
これだけいっぱい間違いを主張して、みんなに指摘してもらってるのだから、
木直田さん、そろそろみんなに感謝するか謝罪すべきなんじゃないか?
286: 2006/11/22(水) 00:45:18 ID:GVSsKEpg(8/12)調 AAS
イラク戦争前のフランス利権は石油だけではなかったとする田中宇氏
の論説があるが、フランス政府がイラク戦争前にイラクから大量に血液調達を行っていた場合、
2003年のイラク戦争開始年にはその利権が失われ、その分だけ別途、血液を
調達せねばならない事になる。
その場合、最も手っ取り早い方法は、自国民を巧妙に殺害することである。
そしてどういう訳か同じ2003年にフランスで異常気象(熱波)名目で
1万5千人も亡くなっているのである。一方、隣国のドイツは全く死んでいない。
外部リンク[html]:www.teamrenzan.com
287: 2006/11/22(水) 00:49:23 ID:81OpjFw/(3/9)調 AAS
分かったわ
要するに>>230には答えられんのね
あんたの負けだなw
さ〜て俺は寝るわw
288: 2006/11/22(水) 00:50:03 ID:0RNKeWH3(3/5)調 AAS
で、その1万5千人から、どれだけの血液ワインが木直田脳内ワイン工房で製造されるの?
ほんのちょっとしか取れないんじゃないの?
289: 2006/11/22(水) 00:53:07 ID:GVSsKEpg(9/12)調 AAS
フランス政府が死体ビジネスとしてのワイン目的に
自国民を大量に殺害するならば、通常のフランス兵やフランス警察部隊を使いにくい。
この目的のためにフランス外人部隊が存在する可能性はないだろうか?
実際、フランス外人部隊はワイン生産村に基地があり、しかもワイン生産工場も
持っているという資料が確認できる。外人部隊の刻印が入ったコルク栓まであり、
当該部隊の負傷退役軍人が雇用されているという。
またフランス外人部隊に参加した日本人の資料を読むと、
この部隊の業務内容はフランス人には難しいが日本人なら可能だといった発言もある。
フランス人がフランス人を殺害するのは確かに心理的に厳しい。
こういった点でも矛盾しない。また今回の時期に合致したイタリア情報部幹部の更迭も
不可解である。やはりワイン生産には血液が必要とされているのではないか、と
考えられても仕方がない状況にあるのは確かだろう。
290: 2006/11/22(水) 00:55:35 ID:GVSsKEpg(10/12)調 AAS
>要するに>>230には答えられんのね
以下のステップ5を加える事によって、既にお答えはできている。
貴方の知能指数はどの程度なのでしょうか?
−−−−−−−−−−−−−−−
ステップ1: 血液をそのまま飲んでいた (旧約聖書時代)
↓
ステップ2: 偶然、自然発酵した血液を飲むようになった
↓
ステップ3: 血液を放置し得られた血清を火入れ濃縮し
エタノール発酵させたもの (恐らく中世)
↓
ステップ4: ステップ3の血清に果汁で補糖を行ったものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
↓
ステップ5: 豊富に得られる果汁に血球もしくは血液を添加したものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
291: 2006/11/22(水) 00:58:09 ID:GVSsKEpg(11/12)調 AAS
>で、その1万5千人から、どれだけの血液ワインが?
以下のステップ5を加える事によって、既にお答えはできている。
ステップ5をとるならば、ベースは果汁なので
一瓶あたりの必要血液量は何桁かは少なくなる。
−−−−−−−−−−−−−−−
ステップ1: 血液をそのまま飲んでいた (旧約聖書時代)
↓
ステップ2: 偶然、自然発酵した血液を飲むようになった
↓
ステップ3: 血液を放置し得られた血清を火入れ濃縮し
エタノール発酵させたもの (恐らく中世)
↓
ステップ4: ステップ3の血清に果汁で補糖を行ったものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
↓
ステップ5: 豊富に得られる果汁に血球もしくは血液を添加したものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
292(1): 2006/11/22(水) 01:00:40 ID:GVSsKEpg(12/12)調 AAS
そもそもフランスは何故、軍隊に外国人からだけなる部隊
を作らないといけなかったのか?
このようなケースは他国にはない。
293(1): 2006/11/22(水) 01:08:12 ID:gdDZz6mh(3/4)調 AAS
>>281
この方向ってそれまでのはどうすんだい?w
>>282
自分で調べれば。恥じかく前に。って十分に恥ずかしいかw
木直田脳内ワイン工房ステップ5での
果汁と血液との割合はどれくらいなんだw
294: 2006/11/22(水) 01:08:58 ID:j6DRainC(1/15)調 AAS
>>292
また始まったよ、新たな妄想がw
295(1): 2006/11/22(水) 01:10:46 ID:H9WiMsnW(1/2)調 AAS
>>293
断言口調の場合は
ソースがない発言はお控えください。
296: 2006/11/22(水) 01:12:41 ID:gdDZz6mh(4/4)調 AAS
あ、そ。
いじるのも飽きたし俺ももう寝るわ。
297(1): 2006/11/22(水) 01:13:38 ID:H9WiMsnW(2/2)調 AAS
以下の仮説なら、現時点までの全てのご指摘に矛盾しません。
現在ではステップ4と5が混在しているのではないでしょうか?
−−−−−−−−−−−−−−−
ステップ1: 血液をそのまま飲んでいた (旧約聖書時代)
↓
ステップ2: 偶然、自然発酵した血液を飲むようになった
↓
ステップ3: 血液を放置し得られた血清を火入れ濃縮し
エタノール発酵させたもの (恐らく中世)
↓
ステップ4: ステップ3の血清に果汁で補糖を行ったものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
↓
ステップ5: 豊富に得られる果汁に血液を添加したものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
298: 2006/11/22(水) 01:31:15 ID:j6DRainC(2/15)調 AAS
>>295
オマエもソースがないのに妄想で断定するのやめようなw
以前に過去スレで話題になった「携帯電話の盗聴云々」に関しても、
【無知】と【希望的観測】しか出せなかった訳だがw
299(1): 2006/11/22(水) 04:00:11 ID:3GWWAUxw(1)調 AAS
先生はワインだけ問題にしてるけどさ、ブランデーとかはどうなん?
ワインから蒸留して作るんだが。
バルサミコみたいな酢もワインから作るね。
あと他の酒、たとえば日本酒や焼酎やビールやウイスキーやウォッカやラムやジンはどうなん?
それ以外の飲み物、例えばトマトジュースやブラッドオレンジジュースや
コーラやドクターペッパーや紅茶や烏龍茶や麦茶やコーヒーはどうなん?
それから醤油や味噌や豆板醤や甜麺醤やオイスターソースや
XO醤やコチュジャンやニョクマムやしょっつるや
トマトケチャップやタバスコやとんかつソースや
ラードやごま油やバターやイチゴジャムや
かき氷のイチゴシロップやあんこやチョコレートはどうなん?
それから、郵便ポストや赤信号や赤ふんどしはどうなん?
300: 2006/11/22(水) 05:25:33 ID:Y+EYoLam(1/2)調 AAS
>>299
カモのソテーのカモの骨髄を潰して作った血のソースをかけるってのもあるし
豚の血を固めた料理や血を固めた血のソーセージなんてのもあるね
血液は食材としても古くから用いられてきたから
ソースとしてだけではなく醤の具材の一部として混ぜて使われてきていたかもしれないね
食と関係ない郵便ポストや赤信号や赤ふんどしが出てくるのは何故かな?
茶化してるつもり?
301(1): 2006/11/22(水) 05:55:51 ID:0RNKeWH3(4/5)調 AAS
結局は計算上明らかに血液の量が足りないから、
果汁の中にちょびっとだけ血液を入れるという製造工程にしたわけね。
血液の方がコストが安いからって言っていたのに、それじゃ、コストダウンにならないね。
木直田脳内ワイン工房も、もっとコストのことも考えないと。
302: 2006/11/22(水) 07:40:29 ID:0RNKeWH3(5/5)調 AAS
>>297
ちなみに旧約聖書での血を飲んでいたという「血」は、先生の好きな隠語だよ。
本当は何を意味しているのから、教会に行って神父様に聞いてごらん。
303: 2006/11/22(水) 07:55:52 ID:RDtqLHTg(1/14)調 AAS
狩猟民族にとって最も身近にある安価な蛋白源は
やはり「人間由来の肉、内臓、血液」だった事には変わりはありません。
慢性的な食糧不足が続いていたのが古代、中世だった以上
宗教的なタブーがない時代や地域は、当然、食していたと考える方が自然です。
人間の体は解体してしまえばDNA鑑定等をしない限り動物と区別がつきません。
内臓料理ハギスが日常化している英国北部で人喰いから見出されたCJDが
英国南部より数倍高いのも事実です。そういった地域では「人間由来の肉、内臓、血液」
を食していると考える方がむしろ論理的です。同じ事が他の地域にも言えるでしょう。
304: 2006/11/22(水) 07:57:50 ID:RDtqLHTg(2/14)調 AAS
従って、今回、お教えいただいた
>カモのソテーのカモの骨髄を潰して作った血のソースをかけるってのもあるし
>豚の血を固めた料理や血を固めた血のソーセージなんてのもあるね
>血液は食材としても古くから用いられてきたから
>ソースとしてだけではなく醤の具材の一部として混ぜて使われてきていたかもしれないね
に関しても「人間由来の肉、内臓、血液」が使われていない方が
むしろ不自然と考えます。各国大使館等によるDNA鑑定が求められるでしょう。
305: 2006/11/22(水) 08:01:03 ID:RDtqLHTg(3/14)調 AAS
また、
>ブランデーとかはどうなん?
>ワインから蒸留して作るんだが。
>バルサミコみたいな酢もワインから作るね。
に関しても、当然、「人間由来の肉、内臓、血液」が使われていない方が
むしろ不自然と考えます。
むしろそう考えないと米国アルカポネ時代の禁酒法の意義が不可解になります。
ワインだけでなく蒸留酒を含む洋酒一般に関して、こういった懸念がない限り
合理性で知られた米国が、たとえ一時期にせよ禁酒法のような不可解な法律を
通すはずがないと考える方が自然です。
306(1): 2006/11/22(水) 08:07:14 ID:RDtqLHTg(4/14)調 AAS
現在でも「人間由来の肉、内臓、血液」は
依然として最もバイオマスが多くかつ安価であるのは間違いありません。
そして一旦、解体してしまえば、他の動物の肉と見分けがつかない。
経済効率性を追求する社会において、使われていない方が
資本主義の原理上、考えにくい。コストがかかる飼育を要する
牛、羊、豚を食材とするより安価だからです。
307: 2006/11/22(水) 08:09:33 ID:RDtqLHTg(5/14)調 AAS
このような背景を考えると、やはり
以下の食文化の変遷に関する仮説は妥当性があると考えますし
現時点では矛盾をきたしておりません。
==========
ステップ1: 血液をそのまま飲んでいた (旧約聖書時代)
↓
ステップ2: 偶然、自然発酵した血液を飲むようになった
↓
ステップ3: 血液を放置し得られた血清を火入れ濃縮し
エタノール発酵させたもの (恐らく中世)
↓
ステップ4: ステップ3の血清に果汁で補糖を行ったものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
↓
ステップ5: 豊富に得られる果汁に血液を添加したものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
308: 2006/11/22(水) 08:09:52 ID:s3uE5L1I(1/2)調 AAS
>>14
>甲州ワインの欧州販売記事は、
>外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
>当方の以下の論説が影響した可能性もある。欧州ワインが血液酒ならば
>本当の意味でのぶどう酒は確かに欧州で売れるだろう。
「ヨーロッパのワインは血でできている」と主張していながら、
どうして甲州ワインが「本当の意味でのぶどう酒」だと思えるのかね?
あんた「日本でも食人が盛ん」とか主張してたじゃねーか。
309(1): 2006/11/22(水) 08:14:02 ID:s3uE5L1I(2/2)調 AAS
>>306
>現在でも「人間由来の肉、内臓、血液」は
>依然として最もバイオマスが多くかつ安価であるのは間違いありません。
>そして一旦、解体してしまえば、他の動物の肉と見分けがつかない。
他の動物の肉と見分けがつかない?
先生は以前「秋田県で見た目のおかしい肉が売られていた。きっと人肉だ」
とか言ってたけど、やっぱりそれは妄想なのね。
310: 2006/11/22(水) 08:16:34 ID:RDtqLHTg(6/14)調 AAS
>>309
ソーセージやひき肉や
>カモのソテーのカモの骨髄を潰して作った血のソースをかけるってのもあるし
>豚の血を固めた料理や血を固めた血のソーセージなんてのもあるね
>血液は食材としても古くから用いられてきたから
>ソースとしてだけではなく醤の具材の一部として混ぜて使われてきていたかもしれないね
のような形になりますと、区別がつきません。
概観で区別がつくのは生肉状態の時のみです。
311: 2006/11/22(水) 08:17:43 ID:RDtqLHTg(7/14)調 AAS
また日本の大手ハム会社が加工しているハムのような形態
になってもやはり区別がつきません。
312: 2006/11/22(水) 08:19:45 ID:RDtqLHTg(8/14)調 AAS
更に言えば、一部の在日朝鮮人が経営している焼肉屋の肉
に関しても概観上およびコスト上不可解です。
313: 2006/11/22(水) 08:23:21 ID:RU8BvHFu(1)調 AAS
>>301
そうそう。
しかも「血を使ってるのは一部の老舗メーカーだけ」とか言ってるし。
老舗じゃないメーカーの方が原材料費が高いってことになっちゃう。
314: 2006/11/22(水) 08:25:11 ID:RDtqLHTg(9/14)調 AAS
在日朝鮮人コミュニティが畜産業界に手を出していない限り
安価な肉資源を、在日朝鮮人・焼肉屋コミュニティに有利に供給する
事は不可能ですが、在日朝鮮人の方が大規模畜産を行っているといった
例はあまり聞きません。その一方で、在日の焼肉屋は非常に多い。
これはコスト的に説明がつきにくいです。
またそういった焼肉屋で提供している生肉に関しても、
一体、何の肉が概観上、判断がつきません。私は豚、牛、鶏ならば
明確に判断がつくよう舌と目を訓練しています。しかし在日の焼肉屋の多くは
概観も味も豚、牛、鶏とは異なる。しかもコストも安い。
彼らは一体何の肉を使っているのか?
315: 2006/11/22(水) 08:27:14 ID:RDtqLHTg(10/14)調 AAS
また朝鮮半島の「犬肉」は本当に犬なのか?
人間の肉の隠語と考えないと肉供給量の説明がつかないのはなぜか?
朝鮮人はヒトを喰う風習があるのを「犬肉文化」と
称しているの可能性を否定できるのか?
316(1): 2006/11/22(水) 08:29:16 ID:RDtqLHTg(11/14)調 AAS
>「ヨーロッパのワインは血でできている」と主張していながら、
>どうして甲州ワインが「本当の意味でのぶどう酒」だと思えるのかね?
欧州からワイン醸造技術を導入した地域は、
やはり同じ問題を抱えている可能性がある点については認めます。
そもそもその過程がNHKのプロジェクトXに、ある程度明確に示されている。
317: 2006/11/22(水) 08:33:21 ID:RDtqLHTg(12/14)調 AAS
>しかも「血を使ってるのは一部の老舗メーカーだけ」とか言ってるし。
これに関しても>>316のとおりです。
ただ、老舗のメーカーは以下に示した「数種類のプロトタイプのワイン」も
ワインの名称を変える形にした上で実際に作っている可能性がある、
だからこそ老舗のブランドを守れるのではないかと考えています。
==========
ステップ1: 血液をそのまま飲んでいた (旧約聖書時代)
↓
ステップ2: 偶然、自然発酵した血液を飲むようになった
↓
ステップ3: 血液を放置し得られた血清を火入れ濃縮し
エタノール発酵させたもの (恐らく中世)
↓
ステップ4: ステップ3の血清に果汁で補糖を行ったものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
↓
ステップ5: 豊富に得られる果汁に血液を添加したものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
318: 2006/11/22(水) 08:34:28 ID:RDtqLHTg(13/14)調 AAS
このような背景を考えると、やはり
以下の食文化の変遷に関する仮説は妥当性があると考えますし
現時点では矛盾をきたしておりません。
==========
ステップ1: 血液をそのまま飲んでいた (旧約聖書時代)
↓
ステップ2: 偶然、自然発酵した血液を飲むようになった
↓
ステップ3: 血液を放置し得られた血清を火入れ濃縮し
エタノール発酵させたもの (恐らく中世)
↓
ステップ4: ステップ3の血清に果汁で補糖を行ったものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
↓
ステップ5: 豊富に得られる果汁に血液を添加したものを
エタノール発酵させたもの (恐らく近代・現代)
319: 2006/11/22(水) 08:36:05 ID:RDtqLHTg(14/14)調 AAS
1.ワインが純粋な葡萄酒ならば何故、フランス政府は
ワインに対するネガティブな健康キャンペーンを行うのか?
2.ワインが純粋な葡萄酒なら何故、鉄分が葡萄そのものより
一桁近く多いのか?元素循環の収支があわない。
3.ワインが純粋な葡萄酒ならば、何故、フランス国民は
この40年間で半分近くまでワイン消費量を劇的に落としたのか?
4.ワインが純粋な葡萄酒ならば、何故、フランス外人部隊は
コルク栓にフランス外人部隊の刻印をつけたワイン製造を行っている
とする資料が確認できるのか?またフランス外人部隊がワイン製造地域に
部隊を構えているのか?
5.ワインが純粋な葡萄酒ならば、何故、ロックフエラーは禁酒法を通したのか?
320: 2006/11/22(水) 09:47:03 ID:/sJjyPQL(1/18)調 AAS
「純粋な」って付け足したのね。
つまり、血液なんてちょっとしか入っていないということにしたんだね。
大部分がぶどうが原料なら、木直田脳内ワイン工房の活性炭を通す過程はいらないね。
321: 2006/11/22(水) 12:12:48 ID:8p3PcokP(1/10)調 AAS
世界の人口・・・・62億人
牛・・・・・・・・14億頭
豚・・・・・・・・9億頭
羊・・・・・・・・10億頭
ヤギ・・・・・・・8億頭
水牛、馬等を含めた大型家畜合計・・・・44億頭
鶏・・・・・・・・・164億羽
FAO2002年
322: 2006/11/22(水) 12:25:55 ID:8p3PcokP(2/10)調 AAS
牛の体重は約300kg。人間の約5倍。豚の体重は約120kg。人間の2倍。
鶏の体重は約2kg。人間の30分の1。
もちろん1年に全部が解体されるわけではないが、
これだけの家畜数があるならば、予想以上の量の血液量を提供できるだろう。
ただ血液の糖だけではワインは造れない以上、
間違いなく葡萄果汁が補糖目的で添加されているであろうが。これで矛盾点は
更に少なくなったと見られる。
==============
世界の人口・・・・62億人
牛・・・・・・・・14億頭
豚・・・・・・・・9億頭
羊・・・・・・・・10億頭
ヤギ・・・・・・・8億頭
水牛、馬等を含めた大型家畜合計・・・・44億頭
鶏・・・・・・・・・164億羽
FAO2002年
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 679 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ
ぬこの手 ぬこTOP 0.153s